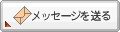2014年01月31日
災難に逢う時節には、災難に逢うがよく候
今日もここに来てくれてありがとうございます。
座禅生活187日目。
堀江貴文氏の新刊「ゼロ」を読みました。
彼はかなり世の中を騒がせたので、みんなよく知っていると思います。
小さい頃から抜群に頭が良くて東大に進学。
東大在学中に起業して、「ライブドア」という会社を立ち上げる。
若き社長として注目を浴び、会社は日本有数のIT企業に発展。
当時ノーネクタイにジャケット、ジーパンのラフな服装で仕事をしていて話題になりました。
自ら起業して自分の生きたいように生きる。
会社勤めに夢を見いだせない若者にとって、憧れの存在でした。
彼の影響を受けて、学校を卒業してから起業する人が増えました。
でもそのクールな姿勢や態度から、いろいろな人から煙たがられました。
雑誌などでもかなり叩かれましたが、彼は気にしない姿勢を取りました。
「言いたいやつには言わせとけばいい」
「たんたんと仕事をしていればいいんだ」
そんな感じで、何を言われても自分の姿勢を崩さないので、さらに嫌われたようです。
彼が書いた「稼ぐが勝ち」という本も、その衝撃的なタイトルと内容から賛否両論でした。
「お金のことしか頭にない守銭奴」とまで言われていました。
その後、自民党から立候補したりしましたが、証券取引法違反で逮捕。
最後まで無罪を訴えましたが、有罪になり、1年9ヶ月を獄中で過ごすことになります。
今回読んだ「ゼロ」と言う本は、いつも強気だった彼のイメージを覆すモノでした。
彼自身怒濤の人生を歩んで、人生観が変わったようです。
内容を一部抜粋すると、
いろいろあって、保身に回った人もいたが、今は誰も恨んでいない。
獄中では死というものをよく考えた。
お金より大事なモノがある。それは信用である。
本当はみんなとつながり、みんなと笑い合いたい。
以前は「分かってもらおうとする姿勢」が足りなかった。
誤解をそのまま放置してしまったのがよくなかった、等々・・・。
彼の好きな言葉は「諸行無常」。
万物は流転する。
すべては流れる川のように、ひとときとして同じ姿をとどめないという意味の言葉。

良寛も同じようなことを言っています。
我が生(しょう) 何処(いずこ)より来たる 去って 何処にか行く
「我が命はどこから(何の為にこの世に生まれて)来たのか。(何の為に生きているのか。そして、
やがて)去ってどこに行くのか」
何もかもが違う2人が、同じような言葉を言っているのが不思議な感じがしました。
堀江氏にとって逮捕収監は、天国から地獄に落ちるような、かなり大きな災難だったはずです。
「ゼロ」では彼が独房で自殺を考えるくらいもがき苦しんだ末、出来事を受け入れ、「いまここ」に落ちついている様子が書かれています。
災難について、良寛はこう言っています。
『災難に逢う時節には、災難に逢うがよく候。
死ぬ時節には、死ぬがよく候。
是ハこれ災難をのがるる妙法にて候』
災難に逢ったら、それから逃げ出そうとせずに、災難に直面するがいい。
死ぬ時がきたら、ジタバタせずに死ぬ覚悟をするがいい。これこそ災難をのがれる妙法なのだ。
昔の堀江氏は当時の部下に対して常にぶっきらぼうで、かなり冷たい態度だったそうです。
それにもかかわらず、その後逮捕収監されたとき、社員から「会社は大丈夫だから、がんばってください」とたくさんの励ましのメッセージが書かれた色紙をもらったといいます。
独房でそのメッセージが書かれた色紙をもらった時、彼は声を出して泣いたそうです。
そしていま「ゼロ」というタイトルにもあるように、すべてを受け入れて「いまここ」に落ち着いています。
本の帯にある彼の写真も落ち着いていて、「あたたかみ」も出てきています。
現状への感謝とすべてを受け入れる覚悟があれば、人生は「恐れるに足らず」です。
今日もここに来てくれてありがとうございました。
人気ブログランキングへ
精神世界ランキング
2014年01月30日
星のように光っては消えていく瞬間が愛おしいです
今日もここに来てくれてありがとうございます。
座禅生活186日目。
昨日は3歳の息子が抱きついてきて、離れませんでした。
寝るときはいつも「おてて」と言って、僕の手を持ってそのまま寝ます。
夜中も僕の手を探して何度も目を覚まし、僕の手があったらそれをつかんで自分の顔の前に持って行って寝ていきます。
朝も僕が起きたら一緒に起きてきて、「幼稚園に行かない」「パパちゃんといっしょにいる」と言い出します。
そんな息子の甘えぶりを、妻は冷たい視線で見ています。
「もうすぐ4歳になるのに、そんなに甘えて・・・」みたいな感じです。
僕も息子が生まれたときは同じ考えでした。
強く育って、世の中をたくましく生きていってほしい。
だから厳しく育てるし、必要以上の甘えはさせない、みたいな考えでした。
でもいまは、すっかり考え方が変わりました。
強さよりも、「安心感」のようなものを小さいときから培って欲しいと思っています。
しっかりした「安心感」という土台があれば、社会がどんな状況になっても、文字通り安心して生きていくことができます。
「安心感」とは「動じない強さ」でもあるのです。
江戸時代に良寛という僧がいました。
彼は「良寛さん」と多くの人に慕われ、全国を放浪しました。
人を愛し、特に子供達を愛し、積極的に遊んだそうです
良寛は「子供の純真な心こそが誠の仏の心」と考え、子供達と遊ぶことを好み、かくれんぼや手毬をついたりしてよく遊んだといいます。
名書家として知られた良寛でしたが、高名な人物からの書の依頼は断る事が多かったそうです。
でも子供達から「凧に文字を書いて欲しい」と頼まれた時には喜んで、『天上大風』(てんじょうたいふう)の字を書いたそうです。
ある日の夕暮れ時、良寛は隠れんぼをして子供達と遊んでいて、自分が隠れる番になり、田んぼにうまく隠れました。
しかし日が暮れて暗くなり、子供達は良寛だけを探し出せないまま家に帰ってしまいました。
翌朝早くにある農夫が田んぼに来ると、そこに良寛が居たので驚いて問いただすと良寛は「静かに!そんな大声を出せば、子供達に見つかってしまうではないか」と言ったそうです。

良寛は、多くの人々から愛されていました。
まったくの無名の僧侶でありながら、人々の情けにより必ず食べ物と着る物は与えられたのです。
僕たちは、存在しているだけで価値があります。
豪邸に住んでいようと、お金があろうと関係ありません。
人は「あたたかみ」によって決まるのです。
あたたかみのある人には人が集まってくるし、いざというときもまわりの人が助けてくれるものです。
自分の存在の価値に目覚めると、「必要な物」は与えられます。
お金でも健康でも何でもです。
では、彼のその「あたたかみ」はどこから来るのか。
幼少期からの「安心」「安全」「信頼」から来るのです。
幼少期に安心を与えられれば、安心感を持ったあたたかい人物になります。
そういう人は成長して大人になって、他の人と「安心」を軸にしたあたたかい人間関係を築く事ができるのです。
「あたたかみ」があればどこでも、誰とでもうまくやっていけるものです。
なぜなら、どんな環境でも最終的には人間同士のつきあいです。
仕事の能力よりも人間性がモノを言うのです。
息子には「あたたかみ」のある人になってほしいと思っています。
彼が甘えてくるのも今だけです。
そのうち、僕なんて相手にされなくなるでしょう。
息子と過ごす時間は、一瞬一瞬がきらめく宝石のように感じます。
今の息子は、今しかいません。
星のように光っては消えていく瞬間瞬間を、「あたたかみ」を持って過ごしたいものです。
今日もここに来てくれてありがとうございました。
人気ブログランキングへ
精神世界ランキング
2014年01月29日
死を目前にしたとき初めて気づくのです
今日もここに来てくれてありがとうございます。
座禅生活185日目。
20世紀は 「科学では人が幸せになれないことを証明した世紀」といわれています。
政治、経済、科学、医学、これらは皆、僕たちを幸福にするためにあるはずです。
資本主義や社会主義など、いろいろな社会体制が試されるのも、僕たちが幸福を求めてのことです。
ではこれまでの社会の発達にもかかわらず、僕たちが幸せになれなかったのはなぜでしょうか。
親鸞聖人は『歎異抄』で、こう断言されています。
「念仏者は無碍の一道である。皆さんも早く、念仏者になって、無碍の一道に出てください。人生の目的だから」。
無碍とは、「さまたげ」や「とらわれ」がないという意味です。
僕たちは人間関係や生活の問題など、いろいろなことに「とらわれ」て、苦しみ悩み不安になっています。
「さまたげ」や「とらわれ」がなくなった世界を親鸞聖人は「無碍の一道」と言っています。
「絶対の幸福」と言ってもいいです。
親鸞聖人は無碍の一道、すなわち「絶対の幸福」こそが人生の目的であると言っているのです。
生きていると色々な問題が、次々にテーマを変えて起こります。
仕事を失ったり、月々の生活費に頭を痛めたり、病気で入退院を繰り返したり、夫の浮気に悩んだり・・・。
逆に健康や財産などに恵まれていたとしても、僕たちは幸せにはなれません。
アタリマエの基準が上がって、「もっと、もっと」と執着が生まれるだけです。

僕たちに欠けている視点があります。
それは現状への感謝です。
普通に生活できて、家で寝起きが出来るだけでも、本当にありがたい事です。
そのうえでの悩みなどは、本当は大した問題ではありません。
「病院のベッドからもう出られない」と覚悟をしている人にとっては、家で寝起きができるだけで本当にうれしいものです。
自分が生かされている原点を忘れない人は、苦も楽も味わえる事を楽しみ、人生を思い切り生きる事が出来ます。
人は何かを失ってから、初めて気づくものです。
「死」というものを本当に目前にしたとき、初めて日常の不満や悩みでさえも「体験できること自体が素晴らしい」と気づくのです。
でも、それでは遅いのです。
今がどんな状況でも、感謝を持って、「いまここ」で幸せを見い出すことです。
なぜなら、僕たちには「今」しかないからです。
今の自分の意識がすべてであり、その意識次第で未来は変わります。
今、生活の中にある幸せに気付きましょう。
そして今の生活の中で、感謝を重ねていきましょう。
今日もここに来てくれてありがとうございました。
人気ブログランキングへ
精神世界ランキング
座禅生活185日目。
20世紀は 「科学では人が幸せになれないことを証明した世紀」といわれています。
政治、経済、科学、医学、これらは皆、僕たちを幸福にするためにあるはずです。
資本主義や社会主義など、いろいろな社会体制が試されるのも、僕たちが幸福を求めてのことです。
ではこれまでの社会の発達にもかかわらず、僕たちが幸せになれなかったのはなぜでしょうか。
親鸞聖人は『歎異抄』で、こう断言されています。
「念仏者は無碍の一道である。皆さんも早く、念仏者になって、無碍の一道に出てください。人生の目的だから」。
無碍とは、「さまたげ」や「とらわれ」がないという意味です。
僕たちは人間関係や生活の問題など、いろいろなことに「とらわれ」て、苦しみ悩み不安になっています。
「さまたげ」や「とらわれ」がなくなった世界を親鸞聖人は「無碍の一道」と言っています。
「絶対の幸福」と言ってもいいです。
親鸞聖人は無碍の一道、すなわち「絶対の幸福」こそが人生の目的であると言っているのです。
生きていると色々な問題が、次々にテーマを変えて起こります。
仕事を失ったり、月々の生活費に頭を痛めたり、病気で入退院を繰り返したり、夫の浮気に悩んだり・・・。
逆に健康や財産などに恵まれていたとしても、僕たちは幸せにはなれません。
アタリマエの基準が上がって、「もっと、もっと」と執着が生まれるだけです。

僕たちに欠けている視点があります。
それは現状への感謝です。
普通に生活できて、家で寝起きが出来るだけでも、本当にありがたい事です。
そのうえでの悩みなどは、本当は大した問題ではありません。
「病院のベッドからもう出られない」と覚悟をしている人にとっては、家で寝起きができるだけで本当にうれしいものです。
自分が生かされている原点を忘れない人は、苦も楽も味わえる事を楽しみ、人生を思い切り生きる事が出来ます。
人は何かを失ってから、初めて気づくものです。
「死」というものを本当に目前にしたとき、初めて日常の不満や悩みでさえも「体験できること自体が素晴らしい」と気づくのです。
でも、それでは遅いのです。
今がどんな状況でも、感謝を持って、「いまここ」で幸せを見い出すことです。
なぜなら、僕たちには「今」しかないからです。
今の自分の意識がすべてであり、その意識次第で未来は変わります。
今、生活の中にある幸せに気付きましょう。
そして今の生活の中で、感謝を重ねていきましょう。
今日もここに来てくれてありがとうございました。
人気ブログランキングへ
精神世界ランキング
2014年01月28日
子供が風邪で寝込んだのは誰のせいでもありません
今日もここに来てくれてありがとうございます。
座禅生活184日目。
一昨日から、息子が風邪で寝込んでいます。
いつも元気で、よくしゃべってよく動く息子。
ぐったりして元気がない様子を見ると、親としてはさすがに心配します。
先週末に鹿児島はかなり気温が上がりました。
日中は暑いくらいで、上着はいりませんでした。
連日からすると気温がいきなり上がったので、その変化にうまく対応ができませんでした。
暖かかったので、少し薄着をさせて、寝るときにも布団を1枚減らしたことが体調を崩す原因になったようです。
2歳まではほとんど風邪を引かない子でした。
3歳になったくらいから、食べ物の好き嫌いが始まり、お菓子の味も知りました。
誰もが通る道ではありますが、好き嫌いをするようになったのも、風邪を引きやすくなった原因だと思います。

親としては普段から気をつけているのですが、「あのときああしとけば」と後悔もあります。
でもあの時、布団を1枚はがさなかったら、彼は風邪を引かなかったのでしょうか。
それは分かりません。
ひいたかもしれないし、ひかなかったかもしれません。
生きていると選択、選択の連続です。
その選択が吉と出る場合もあれば、凶と出る場合もあります。
その場その場で、ベストを尽くして判断するしかありません。
言えることは、親としてできることをやったなら「それでよし」だということです。
中には子供の言いなりで、強く叱れない親もいます。
「この子が小さいときに不憫な思いをさせてしまって悪かった」
「この子がこういう風になったのは、小さいときに~してあげれなかったから」
「子供を満足な環境で育ててあげられなくて、申し訳ない」
そんな理由で自分を責め、子供を強く叱れない親は多いです。
でも親がそうやって自分を責めたところで、何になるのでしょう。
そういう親を持った子供はきっと、無意識に親を恨むようになります。
親子は強い絆でつながっています。
親が子供にそういう気持ちを持っていると、子供は無意識に親のそういう部分を責めるようになります。
被害者は加害者でもあるというゆえんです。
「そのときはそのとき」、「いまはいま」と切り替えることが必要です。
そのときに自分ができることをきちんとやったならば、あとはおまかせです。
どっちにしても親の思うとおりに子供は育ちませんから(笑)。
「子供に迷惑をかけた」ことで逆に子供が強くなって、厳しい社会でもたくましく生きていくことは普通にあります。
やるべきことをやって、あとはおまかせの心境になれば、逆に物事はうまく回り始めるものです。
合い言葉はこれです。
「そのときはそのとき」。
「いまはいま」。
今日もここに来てくれてありがとうございました。
人気ブログランキングへ
精神世界ランキング
2014年01月27日
感謝の量稽古を習慣化させましょう
今日もここに来てくれてありがとうございます。
座禅生活183日目。
今はインターネットで何でも見れるので、本当に便利な時代です。
今日はYoutubeで大相撲を見ていました。
ずっと見ていると、力士の勝ちパターン、負けパターンが分かってきます。
強い力士はいつもの自分でいれば、まず勝てます。
どれだけ落ちついていられるかがポイントです。
弱い力士は最初こそ勝負しますが、流れが悪くなった途端苦し紛れの技を出します。
「引く」とか「いなす」とかです。
弱い力士は地力がないから、最後にはそういう手をださなければならなくなります。
でもそれは通用せず、そのまま負けることがほとんど。
結局は、初めから負ける相撲になっているのです。
気づいていないかもしれませんが、 人が不幸に向かう時は自分から負けパターンをとっているものです。
起きてくる現象は中立です。
中立である現象に対して、僕たちはその良し悪しを判断し、自らを俵に追い込んでるのが真実です。
困ったことがあると、周りの人とか環境のせいにする人は多いです
でも本当に自分を不幸にさせる犯人が、他でもない自分自身であることに気づかなければなりません。

要は、地力を付ける生き方が大事です。
問題があってもあれこれ考え込まずに、やるべきことをきちんとやることが基本。
状況の中で自分が出来る努力さえしていれば、あとは成り行きにまかせる勇気も必要です。
自分ができる努力をした後は、流れに完全に「お任せ」してしまいましょう。
このお任せができないと、必要以上に心配して心を痛めて心身を消耗します。
これが元々の問題以外の、新たな二次被害を引き起こします。
勝つための稽古が力士に必要なように、僕たちも感謝の量稽古が必要です。
感謝を日常の中で習慣化し、 日常生活の中で「ありがとう」「ありがたい」と思いながら生活することです。
これを継続していると、自然と心に感謝が満ちて来ます。
それに応じて、感謝したくなる現実が現れます。
もっというと、そのような現実に「気付く」ことになるのです。
現実は自分が気付いていないだけで、感謝すべきことでいっぱいです。
これまで生活して来れただけでも、十分ではないでしょうか。
日々の努力と共に、生かされていることに「ありがたい」という思いをもって生きていきたいものです。
その思いがあれば、何が起こってもなんとか生きていけるものです。
今日もここに来てくれてありがとうございました。
人気ブログランキングへ
精神世界ランキング