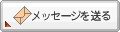2013年08月21日
世界の紛争を解決できますか?
座禅生活47日。滝行4日目
暑い中草むしりをしたらけっこう疲れました。暑さのせいで疲れ方が尋常じゃない。疲れが明日に残らなければいいのですが。
今日ちょっと自分の生活を振り返ってみたんですが、非常に質素なことに気がつきました。ギャンブルも酒もたばこもしない。やることといったら座禅か滝行。テレビも長男が生まれる頃から全く見ない生活。逆算するとまる3年以上まともにテレビを見ていないことになる。テレビがついているときはあるのですが、「お母さんといっしょ」とかの子ども向け番組。もはや息子のためのテレビです。
テレビを見なくてもネットとかでだいたいの社会の状況とか今の話題とかのことは頭に入ってくる。テレビって百害あって一利なしだと思っています。ニュースとかろくなのないからむしろ知らない方が幸せ。正直、社会情勢とか自分には関係ないと思っていました。社会がどんな状況になっても自分さえしっかりしていればいいと思っていました。
しかし、最近「プロセス指向心理学」の考え方を知ってから、物事の見方ががらりと変わりました。

その提唱者アーノルドミンデルの言葉。
「紛争解決とは、世界を構成するすべての部分が実は自分の中にも存在していることを見つけることを助けることである。その外部で起こっているのと同じである自身の中にある紛争の声にまずは耳を傾け、それに平和をもたらすことである。
このことは、私たちは、自分の外界(他人)の部分や声の全てに耳を傾けるのと同時に、自身の中で起こっている全ての声にも深く耳を傾ける必要があるということだ(ディープリスニング)。
紛争を解決するには、まず、ファシリテーターが次のような手法によって、彼自身の内部の紛争を解決することが大変役に立つ。ファシリテーターは奇跡を呼ぶ導師のように、内的な部分としてこれらの部分の全てを知り、自分自身の中で、内的な部分を調和に至らせることに努力し続ける必要がある。それなしには、外的な世界における紛争の解決を助けることなどできはしないのだ。」
頭を殴られたような気がしました。世界の平和を望むなら、まずは自分の中が平和でなければならない。紛争や衝突のない世の中にしたいなら、まずは自分の中をそのような状態にしなければならない。
童話作家かミュージシャンか誰かそんなことを言っていた人がいましたが、このアーノルドミンデルという人は物理学者。同時にユング派の心理学者でもある。そんな人から「まずは自分の内部から・・・」といったような言葉が出てきたのは驚きでした。
ちなみにこの人によると、自己というのは「エコロジカルな自己」。すなわち世界における他の全ての存在を含む概念。となると世の中にあるものはすべてが「私」そのものということになる。
そこにさらに愛というキーワードが出てくる。
ある経済学者の考え方(一般的な自己の考え方)
「あなたにより多くを与えたら、私の取り分は少なくなってしまう」
愛する人が知っていること(エコロジカルな自己の考え方)
「あなたにより多く与えることは、私もより多くを得ることになる。あなたが誰かを愛するならば、彼らの幸せは、あなた自身の幸せである。彼らの苦痛は、あなたの苦痛である。愛しているとき、人は、その他者をもが自分自身の一部であるような感覚になる」
要するに
自分=他者=取り巻く世界
自分の心の平和(幸福)=他者の心の平和=世界平和
自分が幸せになりたければ周りの人や取り巻く世界が幸せになるよう行動すること。そうすれば自分も幸せになれる。周りの人の幸せは自分の幸せ。自分の心が平和になれば世界平和につながる。自己と同じように他を愛せよ。自分がしてほしいことをほかの人にもしてあげなさいという言葉にもつながる。
自分がいかに狭い自己(自我)の中で生きていたか思い知らされました。これからはこれまでの狭い考え方からエコロジカルな自己を意識して生活しようと思います。
暑い中草むしりをしたらけっこう疲れました。暑さのせいで疲れ方が尋常じゃない。疲れが明日に残らなければいいのですが。
今日ちょっと自分の生活を振り返ってみたんですが、非常に質素なことに気がつきました。ギャンブルも酒もたばこもしない。やることといったら座禅か滝行。テレビも長男が生まれる頃から全く見ない生活。逆算するとまる3年以上まともにテレビを見ていないことになる。テレビがついているときはあるのですが、「お母さんといっしょ」とかの子ども向け番組。もはや息子のためのテレビです。
テレビを見なくてもネットとかでだいたいの社会の状況とか今の話題とかのことは頭に入ってくる。テレビって百害あって一利なしだと思っています。ニュースとかろくなのないからむしろ知らない方が幸せ。正直、社会情勢とか自分には関係ないと思っていました。社会がどんな状況になっても自分さえしっかりしていればいいと思っていました。
しかし、最近「プロセス指向心理学」の考え方を知ってから、物事の見方ががらりと変わりました。

その提唱者アーノルドミンデルの言葉。
「紛争解決とは、世界を構成するすべての部分が実は自分の中にも存在していることを見つけることを助けることである。その外部で起こっているのと同じである自身の中にある紛争の声にまずは耳を傾け、それに平和をもたらすことである。
このことは、私たちは、自分の外界(他人)の部分や声の全てに耳を傾けるのと同時に、自身の中で起こっている全ての声にも深く耳を傾ける必要があるということだ(ディープリスニング)。
紛争を解決するには、まず、ファシリテーターが次のような手法によって、彼自身の内部の紛争を解決することが大変役に立つ。ファシリテーターは奇跡を呼ぶ導師のように、内的な部分としてこれらの部分の全てを知り、自分自身の中で、内的な部分を調和に至らせることに努力し続ける必要がある。それなしには、外的な世界における紛争の解決を助けることなどできはしないのだ。」
頭を殴られたような気がしました。世界の平和を望むなら、まずは自分の中が平和でなければならない。紛争や衝突のない世の中にしたいなら、まずは自分の中をそのような状態にしなければならない。
童話作家かミュージシャンか誰かそんなことを言っていた人がいましたが、このアーノルドミンデルという人は物理学者。同時にユング派の心理学者でもある。そんな人から「まずは自分の内部から・・・」といったような言葉が出てきたのは驚きでした。
ちなみにこの人によると、自己というのは「エコロジカルな自己」。すなわち世界における他の全ての存在を含む概念。となると世の中にあるものはすべてが「私」そのものということになる。
そこにさらに愛というキーワードが出てくる。
ある経済学者の考え方(一般的な自己の考え方)
「あなたにより多くを与えたら、私の取り分は少なくなってしまう」
愛する人が知っていること(エコロジカルな自己の考え方)
「あなたにより多く与えることは、私もより多くを得ることになる。あなたが誰かを愛するならば、彼らの幸せは、あなた自身の幸せである。彼らの苦痛は、あなたの苦痛である。愛しているとき、人は、その他者をもが自分自身の一部であるような感覚になる」
要するに
自分=他者=取り巻く世界
自分の心の平和(幸福)=他者の心の平和=世界平和
自分が幸せになりたければ周りの人や取り巻く世界が幸せになるよう行動すること。そうすれば自分も幸せになれる。周りの人の幸せは自分の幸せ。自分の心が平和になれば世界平和につながる。自己と同じように他を愛せよ。自分がしてほしいことをほかの人にもしてあげなさいという言葉にもつながる。
自分がいかに狭い自己(自我)の中で生きていたか思い知らされました。これからはこれまでの狭い考え方からエコロジカルな自己を意識して生活しようと思います。